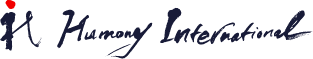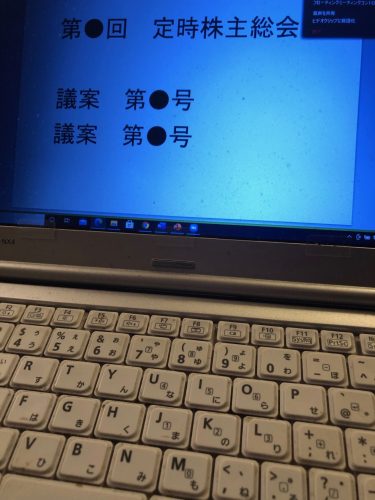 コロナ禍の中、感染拡大を防ぐために企業に強く要請されたのが「リモートワーク導入」です。実際、リモートワークやリモート会議は拡大し、勤務体制や資源配分の抜本的な見直しに取り組む企業も増えています。
コロナ禍の中、感染拡大を防ぐために企業に強く要請されたのが「リモートワーク導入」です。実際、リモートワークやリモート会議は拡大し、勤務体制や資源配分の抜本的な見直しに取り組む企業も増えています。
コロナ禍とバーチャル株主総会
その一方で、リモートへの移行がこれまでなかなか簡単ではなかったものもあります。その一つが株主総会です。 日本における株主総会のこれまでのイメージは「拍手」や「怒声」でしょう。株主総会と言えば、会議場に株主が実際に集まって議決を行うものでした。しかし近年では「電磁的方法による議決権の行使」や「株主総会資料の電子提供制度」などが導入され、一部をバーチャルで開催することが可能となりました。
日本における株主総会のこれまでのイメージは「拍手」や「怒声」でしょう。株主総会と言えば、会議場に株主が実際に集まって議決を行うものでした。しかし近年では「電磁的方法による議決権の行使」や「株主総会資料の電子提供制度」などが導入され、一部をバーチャルで開催することが可能となりました。
もちろん、コロナ禍にかかわらず、株主総会へのリモート参加の環境を整備することは有益です。株主は必ずしも総会の場所の近くに住んでいるわけではないからです。しかし、とりわけコロナ禍の中、これらの制度は去年から積極的に利用され、クラスター防止に貢献してきました。
もっとも、これまでの制度改正は、「完全バーチャル」は想定できていませんでした。その最大の理由は、会社法において、株主総会の「場所」を定めなければならないとされているためです(第298条)。「完全バーチャル」では、そもそも「場所」が定義できなくなります。
しかし、感染拡大防止の取り組みが引き続き求められる中、本年、「産業競争力強化法」の改正の一環として、上場会社が経済産業大臣および法務大臣による確認を受けることで、「場所」を定めない「完全バーチャル」の株主総会を開催できるようにする法案が提出されています。日本では3月決算の企業が多いため、株主総会シーズンは6月下旬となりますが、この法案が成立し、今年の株主総会シーズンからバーチャル総会が増えていけば、会社のあり方が変わる一つの契機になるでしょう。
会社の「場所」とは?
株主総会の例が示すように、これまで会社は、物理的な「場所」に「所在」しており、それは誰の目にもすぐにわかることが前提とされてきました。
例えば、会社法第4条で、「会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする」とされているほか、第49条では、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」とされています。また、第27条により、株式会社の定款には「本店の所在地」を書かなければならず、第31条により、株式会社は定款をその「本店及び支店」に備え置かなければなりません。
しかし、血や肉といった具体的な実体を伴う「自然人」に対し、「法人」はもともと抽象的なものです。現在の制度は、本来は概念的な存在である会社を、「本店」などの仕組みを通じて人為的に特定の場所に紐付け、「準拠法」や「裁判管轄」を明確にしたり、課税を行えるようにしてきたともいえます。
そして、デジタル技術革新は、「場所」の定義を難しくするものでもあります。
デジタル技術がもたらした変化として、「地球の裏側にいる相手とでも瞬時にメッセ―ジがやり取りできる」、「インターネット経由で世界中の会社のサービスにアクセスできる」など、地理的制約を簡単に超えられることが挙げられます。今や、特定のオフィスを持たず、社員全員がそれぞれ各国にある自宅からリモートワークをする会社すら、技術的には実現可能です。そうなると、会社の「所在地」や取引の「場所」は相対的なものになっていきます。
もちろん、この場合でも、「とにかくどこかに本店の場所を決めろ(例:誰かの家を本店として登記しろ)」と法律で要求することはできるでしょう。しかし、そうなると、「では、なるべく税金の安い所に」など、場所を「選ぶ」行為も増えるでしょう。結果、その「場所」が実態と合わなくなり、課税や規制監督などを十分に行えなくなるかもしれません。現在、世界的に話題を集めているグローバル企業への課税問題も、このような視点から捉えることができます。
デジタル化があぶり出す企業の姿
前述のように、法人はもともと概念上の産物ですので、デジタル化の下で起こっていることは、会社が本来想定されていた姿に近づきつつあるともいえます。
冒頭の株主総会の変化はあくまで一例であり、デジタル化は「会社」のスタイルそのものを変えていきます。デジタル技術革新の下、企業は、生産に必要な人員や技術の確保など、これまでは内部的に「組織」で解決してきたことを、アウトソーシングによる外部リソースの活用をはじめ、「市場」で解決できるようになっています。これにより会社は「選択と集中」による資源の再配分や得意分野への注力など、思い切った戦略を取ることも可能になっています。
これまで会社のイメージを象徴していた「本社建物」や「会議室」、「金庫」などに代わり、これからの会社は、その理念やコンセプトを軸として、さまざまなリソースを束ねる「ネットワーク」や「結節点」としての性格を強めていくことになります。これに伴い、会社の「内部」と「外部」の区別も希薄化していくでしょう。
技術革新の流れを止めることは難しい以上、会社の変化も止めることは難しいでしょう。この流れの中で必要なことは、これからの企業を無理やり「場所」や「ペーパーワーク」、「押印」などの従来からの企業像にはめ込むことではなく、新技術を活かせる新しい企業像を創っていくことです。
すでにデジタル技術は、通勤地獄や引っ越しに伴う退職、ペーパーワークや押印文化、自前主義の慣行などを見直す機会を提供しています。一方で、デジタルでかなりのことが行えるようになったからこそ、対面という貴重な機会を有効に使う必要があります。そうした貴重な時間をペーパーワークや押印に費やすのは、ますますもったいないのです。今後とも、取引実務や慣行、事務の進め方、制度などを包括的に見直し、デジタル化に適したエコシステムを構築していくことが求められます。
会社のガバナンスに求められること
このような変化は、会社の「ガバナンス」も変えていくでしょう。
例えば、これまで道路交通の安全を確保する上で必要なことは、「運転者の技能や知識の水準維持」であり、この観点から運転免許制度が設けられてきました。しかし、今後自動運転が普及していくと、交通安全を確保していく上では、「自動運転プログラムの妥当性や入力データのチェック」が、より重要になってくるでしょう。
同様に、会社のガバナンスを考える上でも、「会社はどこにあるのか」、「株主総会はどこで開催されるのか」に代わり、会社がどのようなネットワークでどこと繋がり、いかなるデータを集め、どう活用しているのか等がより重要になっていくでしょう。
目先の株主総会シーズンについて言えば、「バーチャル参加の環境整備に努める会社は、幅広い株主の参加を後押しする開かれた会社である」といった評価が社会に拡がるかどうかが一つの鍵でしょう。かつて、日本における「株主総会の一斉開催」が社会的に問題になったように、会社からすれば、株主を総会に来させない(=株主総会をシャンシャンとつつがなく終わらせる)簡単な手は、株主にとって不便なタイミングに、対面だけで総会を開催することなのです。この点では、世論が、デジタル技術を活用した株主との対話を重視する会社をなるべく後押しすることも、日本のDXにとって重要であるように感じます。
連載第31回「ITと地球温暖化問題」(4月14日掲載予定)